

引っ越しはダメ!!【土用】 2023~2024
土用殺方位 2025~2026

暦を見ると、年に4回ほど『土用』というものがあります。
この『土用』とはいったい何なんでしょうか?
7月の「土用の丑」の日にはうなぎを食べる習慣もあるので、ご存じのことと思います。春夏秋冬の四季の中で、土用の作用とは何かというと、季節を調節する役目をになっているといえます。自然の循環は、春から夏、夏から秋、秋から冬、そして冬から春へと、順次移行していきますが、その四季を訓節し変化させていくのが、この土用の土気の作用であるといわれています。
土用殺とは、毎年夏至の前後の約20日間、土用と呼ばれる期間に訪れるとされる、各方角のうち1つの方位に対して強い“殺気”が発生するとされる風水の概念です。土用殺方位は、その強い殺気が発生する方位のことを指します。土用殺方位は風水学において、土星が影響を与える方角のことを指します。土用殺方位は、西南に位置し、土星が影響を与えることで、不運や災厄を引き起こす可能性があるとされています。そのため、土用殺方位には、不要な物や不要な人間などを遠ざけるために、広い空間や障害物を置くことが推奨されています。また、土用殺方位には、風水上、火を使った装飾や照明などを使用することで、不運を鎮める効果があるとされています。
土用殺方位に対する風水の考え方は、土用殺方位に対してはその方角を避けるべきであるとされています。また、土用殺方位に対して強く感じる場合は、対策を施すことが望ましいとされています。
具体的な対策としては、以下のようなものがあります。
土用殺方位を避けるためには、その方位に対する家族の行動を制限したり、その方位にある部屋を使わないようにするなどの対策が有効です。また、風水的にはその方位に、金属製の風鈴や五行に属する水を置くことで、土用殺方位の気を吸い取ることができるとされています。
水は風水において、財運を引き寄せる力があるとされています。土用殺方位に対して水を置くことで、土用殺方位の強い殺気を鎮めることができます。水を置く場所としては、その方位に対しての玄関、窓やベランダなどが良いでしょう。
風水アイテムを使うことで、土用殺方位の強い殺気を和らげることができます。例えば、五行に属する木を使った置物や観葉植物、また風鈴や光を反射させるクリスタルなどが有効です。
空間を浄化することで、土用殺方位の強い殺気を和らげることができます。空間を浄化する方法としては、セージやホワイトセージなどのハーブを燃やす、水晶を使った浄化などがあります。
土用の時期は、土気の作用が最も強くあらわれるのです。土には大地のすべてのものを育む力と、使命を終えて枯れていくものを土にかえす力とがあり、「土は生殺二道を司る」といわれるように、あらゆるものを変化させる力をもっているのです。中でも、土用の時期の土は細菌の働きも活発で、ものを育てる力より、ものを腐らせる力のほうが強く作用します。そのため、昔から土用の時期に土いじりをすると、心身の健康を害するといわれてきました。
木星の気
火星の気
一金星の気
水星の気
まず、四季の配置はこのようになっています。これら四つの気にし気が入ることによって、五気の関係が四季の変化を生み、自然の調和をなすのです。では、土用の期間を見てみましょう。相性のよし悪しも、この五気の関係が自然に順じているかいないかが、基本になるわけです。私たちは自然の摂理にさからうことはできません。より自然に順応した生き方をすることが、自分のよさを表現するための殼人の武器になるといえます。土地を購人したり、家を建てる際にも、この上用の作用を知っておくとよいでしょう。
- 1月丑の月の土用…2月の立春までの約18日間
- 4月辰の月の土用…5月の立夏までの約18日間
- 7月未の月の土用…8月の立秋までの約18日間
- 10月戌の月の土用…11月の立冬までの約18日間
※「本命卦」は当たらない?【8種類の八卦・風水の方位】2021
季節の節目の「土用」は健康面に注意すべき
.jpg)
昔から、暦を見て、地鎮祭や棟上式などが行われてきましたが、暦で必ず確認した事柄のひとつに土用があります。土用は、二十四節気の、立春、立夏、立秋、立冬の前の季節の節目となる約一八日間をさし、一年に四度訪れます。五行思想に基づき、物を変化させる「土」、働きを意味する「用」で、それぞれの季節の万物を、土用によって変じ、替える作用をするとされています。
季節の節目である土用は、朝夕の温度変化が大きいため、体調などにも注意したい時期でもあります。土用の中でも一般的に知られているのは、立秋(八月八、九日ころ)の前の夏の土用で、梅雨が明け、暑い夏が訪れるころです。暑さを乗り切るために、十二支の丑にあたる土用の丑の日には、昔から、うなぎや牛肉などを食べて体力をつけたり、梅雨の間干せなかった衣類を土用干しするなどが行われてきました。
家相では、土用期間中は、土気(土が含む気)が盛んな時期なので、この期間中は土木工事のような土を犯す工事をすることは凶とされてきました。「家を建てるな」「土を掘るな」などと伝えられ、大工・土工職人に対しても、土用には、仕事をするなと言われてきました。特に夏の土用は、暑さのために、仕事はつらく、食中毒なども起こりやすく、健康面からも職人の仕事が避けられてきたようです。季節の変わり目は、体に大きな負担がかかります。現代でも、夏の土用以外でも、土用は迷信として扱わず、引っ越しや工事は余裕があれば避けてほしいと考えています。引っ越しでも工事でも、朝は冷え込み、昼は暑いこともあるでしょう。また、季節の変わり目には、高齢者が亡くなることも少なくないと言われてきました。朝夕の温度変化が、体に負担を与えるからでしょう。住まいづくりは、心身ともに大きな負担がかかります。家族の健康だけではなく、家づくりに携わる職人にも配慮し、心の余裕をもって望んで欲しいものです。
土用の期間中は新築・転居は避ける
季節の変わり目にあたる土用は家の運勢を衰退させると言われます。家の新・改築や転居などは、「土用」の時期を 避けるようにしましょう。土用といえばふつう夏の土川をさしますが、本 来は春・夏・秋・冬の4回あります。春の土川は立夏の前、夏の十用は立秋の前、秋 の土用は立冬の前、冬の土用は立春の前で、それ ぞれ18日問をさします。土用は、自然界を変化させる気を意味し、季節 の移り変わりも十用の気によって起こります。し かし、土用は物事を衰退させる殺気もあわせもっ ています。そのため、この時期は新築や転居をす ると、運勢が下降していきます。
たとえ吉方位への移動であっても、また転居先の住まいが吉相であっても、土用の殺気がすべて を打ち消してしまいます。5月の連休に転居をする場合も多いようです が、風水学的に見れば、立夏が過ぎるまでは待っ たほうが賢明です。
|
新品価格 |
 |
![]()
土用の期間中は開業禁止
新しい事業の開始や事業の拡大など、新規のビジネス活動は避けるべきです。土用期間はエネルギーが不安定であり、新たな始まりを避ける方が良いとされています。土用期間は、エネルギーの変動が著しい時期であり、新たな事業を始めることが物事の流れを不安定にする可能性があるとされています。
新しい事業は計画や準備が必要であり、順調にスタートさせるためには安定したエネルギーが必要です。土用期間はその安定感が欠如しているため、新規事業の開始を避け、既存の事業や計画の安定を図ることが推奨されます。また、開業は新たなスタートや挑戦を意味しますが、土用期間中は変化が起こりやすいため、計画外のトラブルや課題が生じる可能性が高まります。このため、土用期間中は慎重になり、既存の事業を安定させる方が良いとされています。
総じて、開業禁止の制約は土用期間中の安定性維持を目的としており、新しい始まりを避け、安全な状態を維持することが重要視されています。
土用は伐採も禁止
木を切る伐採活動も土用期間中は慎重になるべきです。木には自然のエネルギーが宿っており、そのエネルギーの変化が土用期間に影響を与える可能性があるためです。
木には自然のエネルギーが宿っており、そのエネルギーは土用期間中においても変化を遂げると考えられています。したがって、木を伐採することはそのエネルギーの変動を引き起こす可能性があり、これが土用期間の不安定さに影響を与える可能性があるためです。
さらに、伐採行為は自然環境に対する影響を持つため、土用期間中は環境への慎重な配慮が求められます。木々は生態系において重要な存在であり、そのバランスを崩すことが環境への悪影響を引き起こす可能性があるからです。土用期間は一般にエネルギーの変動が激しい時期であり、これにより木のエネルギーも特に敏感になるとされています。そのため、伐採行為は土用期間中は慎重に検討し、できるだけ控えるべきだとされています。総括すると、伐採禁止の制限は環境保護とエネルギーの安定性の観点から導入されており、土用期間中の木の取り扱いには慎重なアプローチが求められています。
土用の期間中はこの方位に注意
十用の間はどの方位への新築、転居も避けたほうがよいのですが、なかでも土用に入る月の十二支が示す方位は殺気が強くなります。春の土用の入りは4月辰月なので辰の方位(東南)、夏の土用の入りは7月未月なので末の方位(南西)、秋の十用の入りは10月戌月なので戌の方位(西北)、冬の七川の入りは丑月なので丑の方位(東北)が要注意です。
土用の期間中の注意点
「土用」とは、太陽黄経が150度から180度の期間のことで、一般的には4回あります。それぞれ「春の土用」「夏の土用」「秋の土用」「冬の土用」と呼ばれます。土用期間中には、風水において運気が下がりやすいとされる「土用神」と呼ばれる方位があり、特に「土用の入り」や「土用の仏滅」には注意が必要です。以下では、土用期間中の注意点について詳しく説明します。
【土用の入り】
土用の入りは、土用が始まる日のことを指します。風水的には、この日には家の中を大掃除して、気を清めることが望ましいとされています。具体的には、以下のようなことが挙げられます。
・家中の掃除を徹底する
・古いものを捨てる
・不要なものを整理する
・換気をよくする
・新しいものを取り入れる
これらの行動によって、家のエネルギーを浄化し、良い運気を取り入れることができます。
【土用の仏滅】
土用の仏滅は、土用期間中に仏滅が重なる日のことを指します。仏滅は、仏教において吉日ではないとされる日で、風水においても不吉な日とされています。土用の仏滅には、以下のような注意点があります。
・外出を控える
・取引や契約をしない
・重要なイベントを避ける
・病気の人は無理をしない
これらの注意点によって、不幸や災いを回避し、良い運気を維持することができます。
【土用神】
土用神は、土用期間中に風水的に運気が下がりやすい方位のことを指します。土用神には、以下のような特徴があります。
・南東方位に位置する
・青色や黒色の飾り物で飾る
・清めることが必要
土用神がある部屋や場所には、良くないエネルギーが集まりやすくなるため、運気が下がりやすくなります。そこで、土用期間中には、土用神の方位に対する対策が必要となります。具体的には、以下のようなことが挙げられます。
【土用殺2025】避けるべきこと、食べるべきもの、過ごし方

1. 日本の暦、雑節とは?土用とは何か?
日本の暦は、太陽の動きに基づいて作られた二十四節気(立春、夏至など)や五節句(端午の節句など)に加え、季節の移り変わりをより細かく示すために「雑節」と呼ばれる暦日があります。土用は、この雑節の一つで、立春、立夏、立秋、立冬の直前、それぞれ約18日間ずつ存在し、一年で計72日間ほどあります。
2. 土用の由来 - 陰陽五行説と土公神
土用の起源は、古代中国の思想「陰陽五行説」に遡ります。この思想では、万物は「木・火・土・金・水」の5つの要素から成り立ち、互いに影響しあうと考えられています。四季もこの五行に当てはめられ、春は「木」、夏は「火」、秋は「金」、冬は「水」に対応します。そして、それぞれの季節の変わり目である土用は「土」に対応し、万物を生み出す源と考えられてきました。
土用期間中は、土を司る神様「土公神」が土の中にいるとされ、土を動かすことや新しいことを始めることは縁起が悪いとされてきました。これは、農作業が盛んだった時代に、土公神を敬い、自然の恵みに感謝する心から生まれた風習と考えられています。
3. 2025年の土用期間と間日 【いつが土用?間日とは?】
2025年の土用期間と、土公神が天上界へ行き、土を動かすことが許される「間日」は以下の通りです。
季節土用期間間日
冬の土用2025年1月17日~2月2日1月21日、22日、24日、2月2日
春の土用2025年4月17日~5月4日4月18日、19日、22日、30日、5月1日、4日
夏の土用2025年7月19日~8月6日7月21日、22日、26日、8月2日、3日
秋の土用2025年10月20日~11月6日10月21日、29日、31日、11月2日
間日とは、土用期間中であっても、土公神が天上界にいるため、土を動かすことや新しいことを始めても良いとされる日のことです。
※鬼門を防ぐ方法!!【張り・欠け・火気・トイレは避けるべき】
4. 土用期間にやってはいけないこと
土用期間中は、以下のことを控えるべきとされています。
土を動かすこと
土いじり、ガーデニング
草むしり、草刈り
井戸掘り、穴掘り
増改築、リフォーム
地鎮祭、起工式
新しいこと
新居購入、引っ越し
就職、転職
結婚、結納
開業、開店
新しい習い事、趣味を始める
方角に関すること
旅行、長期出張
移転、転居
ただし、間日であればこれらの行為を行っても良いとされています。
5. 土用期間に食べるべきもの 【季節の食材で体調を整える】
土用期間は、季節の変わり目であり、体調を崩しやすい時期でもあります。それぞれの季節の土用には、以下のような食べ物を食べると良いとされています。
【冬土用】
「未の日」に「ひ」のつく食べ物や赤い食材 (例: ヒラメ、ヒラマサ、ひじき、ひよこ豆、トマト、パプリカ、りんごなど)
体を温める根菜類 (例: 大根、にんじん、ごぼうなど)
旬の柑橘類 (例: みかん、ゆず、レモンなど)
【春土用】
「戌の日」に「い」のつく食べ物や白い食材 (例: いわし、いくら、しらす、いか、いちご、芋、大根、かぶ、いんげんなど)
春野菜 (例: たけのこ、菜の花、アスパラガスなど)
山菜 (例: ぜんまい、わらび、ふきなど)
【夏土用】
「丑の日」に「う」のつく食べ物や黒い食材 (例: うなぎ、うどん、瓜、梅干し、土用しじみ、土用卵、土用餅など)
夏野菜 (例: きゅうり、トマト、ナスなど)
水分補給に良い果物 (例: スイカ、梨、ぶどうなど)
【秋土用】
「辰の日」に「た」のつく食べ物や青い食材 (例: サンマ、たこ、大根、玉ねぎ、たけのこなど)
秋の味覚 (例: さつまいも、かぼちゃ、きのこなど)
体を潤す果物 (例: 柿、ぶどう、りんごなど)
これらの食べ物は、季節の変わり目に不足しがちな栄養を補給し、体調を整えるのに役立つとされています。
6. 土用に関する様々な風習【伝統と知恵】
土用期間には、以下のような様々な風習があります。
夏の土用の丑の日にうなぎを食べる習慣。夏バテ防止のために栄養価の高いうなぎを食べるという風習は、江戸時代に平賀源内が考案したと言われています。
夏の土用にしじみを食べる習慣。しじみは肝臓の働きを助け、夏バテ予防に効果があると言われています。
夏の土用に食べるあんこ餅。暑気払いの意味があり、無病息災を願って食べられます。
夏の土用に行われる衣類や書籍、梅、水田の陰干し。衣類や書籍は虫やカビを防ぎ、梅は天日干しで殺菌効果を高めます。水田の土用干しは、土中の有害ガスを抜き、稲の生育を助ける効果があります。
夏の土用中に行う煤払い。家の中を清潔に保ち、厄を払う意味があります。
これらの風習は、暑さを乗り切り、健康に過ごすための知恵として受け継がれてきました。
7. まとめ【土用を上手に過ごすために】
土用は、日本の風土や文化に根ざした暦の区分であり、季節の移り変わりを感じながら、健康に過ごすための知恵が込められています。土用期間を上手に過ごすためには、以下の点に注意しましょう。
- 土用期間と間日を把握し、控えるべきことは避け、行っても良いことは間日に行う。
- 季節の食材を積極的に食べ、体調を整える。
- 土用に関する様々な風習を参考に、心身ともにリフレッシュする。
土用期間を上手に過ごすことで、一年を健康で快適に過ごすことができるでしょう。
土用殺は毎年、太陽が黄経120度、150度、180度、210度、240度、270度、300度、330度に位置する期間のことを指します。この期間中に家屋や建物の工事やリフォーム、土木工事などを行うと、風水的には悪影響を与えるとされています。
土用殺方位は、土用殺が発生する期間中に建物の方位によって決まります。例えば、今年の土用殺期間中に南東向きの建物を建てると、南東が土用殺方位となります。土用殺方位は、年ごとに変化するため、毎年注意が必要です。土用殺方位には、家屋の安定性が低下するため、建物の寿命を縮める、住民の健康に悪影響を与える、家族関係に悪影響を与えるなどの悪影響があるとされています。特に、土用殺期間中に家を建てることは、その家族の運勢に悪影響を与える可能性があります。
風水的には、土用殺期間中には家や建物の工事を行わず、できるだけ静かに過ごすことが望ましいとされています。また、土用殺方位に対する対策としては、土用期間中に家族が使う方角を変える、風水グッズを使う、福徳神を祀るなどがあります。一方で、土用殺方位は、風水においても一種のエネルギーであり、運気を上げるための方位としても扱われています。風水師によっては、土用期間中に特定の方位を活用する方法を提案することもあるようですが、個人的には土用期間中には慎重に行動することが重要だと思われます。
※記事内には「PR」の宣伝活動および、アフィリエイト広告が含まれております。
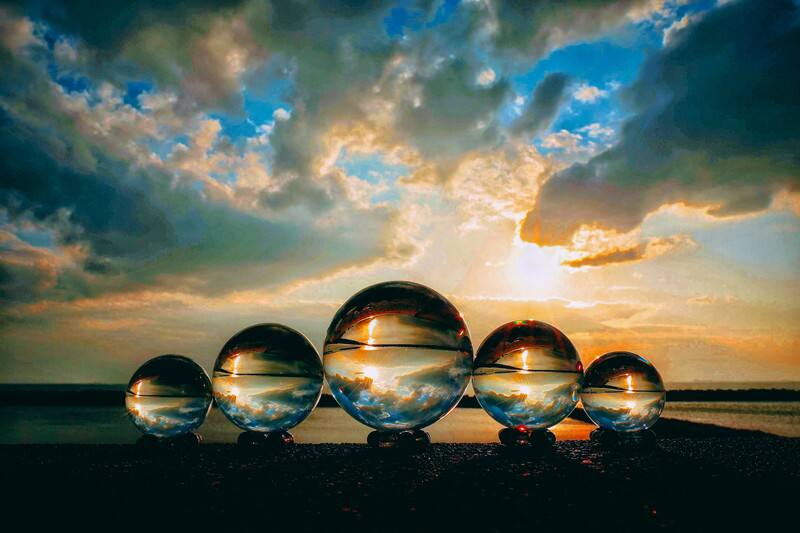

.jpg)

.jpg)





