

良い地相・悪い地相 風水の土地選び2019~2020
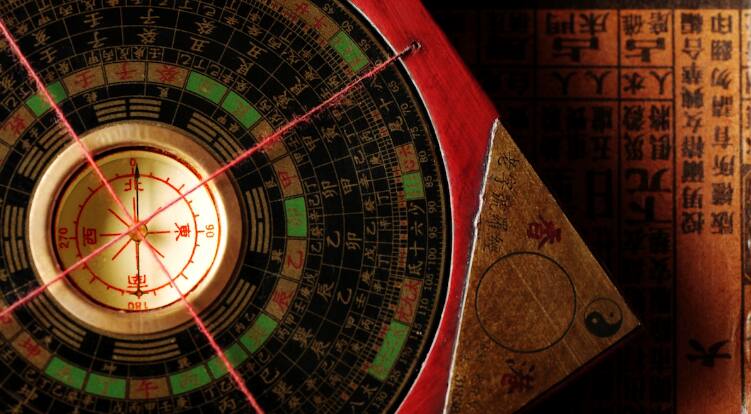
「良い地相」と「悪い地相」
家を建てるのだから、家の外観や間取りにだけ注意すればいいと思うのは大間違いと言えるでしょう。どんな土地に家を建てるかが、実はとても重要なことなのです。土地が発する気は、確実に家や人に影響を及ぼすのです。とはいえ、土地の判断はなかなか難しいものと言えるでしょう。ここでは具体例を挙げながら、風水学から見た「いい土地」の見分け方を詳しく解説していきます。
|
新品価格 |
 |
![]()
よい地相と悪い地相の見分け方
家を建てるときに、風水で最も大切にするのが「土地選び」ではないでしょうか。大地には大きなエネルギーが満ちています。これを上手に取り入れることか、幸せな家づくりの最初のポイントです。いくら理想的な間取りの家にしても、そもそも建っている土地がよいものでなければ、せっかくの設計も効果を発揮できません。家は土地に属するもの。どんな家に住むかよりも、どんな土地に住むかが、そこに住む人に大きな影響を与えるのです。
古来、風水師の仕事というのも、まずは山野を駆け巡り、理想的な土地を探すことが第一でした。よい土地さえ見つけることができれば、家づくりは半ば成功したといってもいいでしょう。この「よい土地」というのは、別の言葉でいうなら、「家相」に対する「地相」だといってもいいでしょう。まずは、よい地相の土地を見つけることなのです。家相と地相がともに整って、初めて家に幸運を呼び込むことができるわけです。
風水における「良い地相」
風水における「良い地相」とは、土地の形状、風水的な気の流れや水の流れ、周囲の地形や環境などが良い状態に整っていることを指します。具体的には、以下のような要素が良い地相に含まれます。
土地の形状
均整の取れた形状で、安定感があることが望ましい。
風水的な気の流れ
自然な流れを妨げず、家の周囲に流れる風水的な気が円滑に流れることが望ましい。また、直線的な通路がなく、曲線的な動線をつくることで、気の流れを良くすることができます。
水の流れ
清潔で自然な水の流れがあると良い地相とされています。ただし、水の流れが直線的で急峻な場合は、激しい気の流れが生じるため、適度な湾曲をもたせることが望ましいとされています。
周囲の地形や環境
周囲に自然が多く、景色が開けていることが良い地相とされています。また、山や高台に囲まれた場所は気が停滞しやすいため、適度な開けた場所にある土地が良いとされています。
日当たり
家が南向きで、明るく日当たりがよい場所が望ましいとされています。
陽気のある南向きの土地
南向きは、一日のうちで最も多くの日光を取り入れることができ、明るく暖かい場所です。風水では陽気が良いとされ、健康や繁栄につながるとされています。
開けた広場や平地
周囲に高い建物や山がなく、開けた広場や平地は、風水的にも開放感があり、吉相とされます。
自然の水が流れる場所
風水では、自然の水が流れる場所は、清浄で健康に良いとされています。川や湖、滝、泉など自然の水の流れがある場所は、繁栄や健康に繋がるとされます。
風通しが良く、気流が良い場所
風通しが良い場所は、汚れた空気を逃がし、新鮮な空気を取り入れることができます。また、気流が良い場所は、陽気が通り抜けやすく、繁栄に良いとされています。
土地が平らで、形が整った場所
風水では、土地が平らで形が整った場所は、安定感があるとされ、健康や安定した生活に繋がるとされています。
これらの要素が揃った場所は、風水的には「瑞気がある」とされ、健康や繁栄に繋がるとされます。一方、悪い地相とされる場所には、龍脈(りゅうみゃく)が通っておらず、自然のエネルギーが乏しい場所があり、そうした場所は風水的に避けられる傾向があります。風水的には環境が良く、健康や幸福、繁栄をもたらす場所とされています。ただし、すべてが完璧に揃っている場所は稀であるため、そこそこの良い状態であれば問題ないとされています。
風水における「悪い地相」
風水における「悪い地相」とは、生気のエネルギーが低下する場所や、負のエネルギーが集まる場所のことを指します。 主なものには以下のようなものがあります。
- 病気地帯(病気を招きやすい土地)
- 狭い路地や道路の突き当たり(生気の停滞)
- 大きな木や建物高いところに囲まれた場所(生気の遮断)
- 不浄地帯(ゴミ捨て場や下水道など)
- 古墳や霊場の近く(負のエネルギーの影響)
また、これらの場所に住んでしまった場合には、風水的な改善を行うことで、生気の流れを整えることができます。
直線状地盤
地盤が直線的であると、陰陽の流れが滞り、災いを招きやすいとされています。 特に、通り道が直線的である場合には、悪い地相とされます。
崖地盤
急な斜面の上に家を建てる場合、陰陽の流れが悪く、住む人の健康や運勢に悪影響を及ぼすとされています。
交差点
交差点の角に家を建てると、陰陽の流れが乱れ、家族間のトラブルや災いを招きとされています。
窪地
低い場所に住居を建てると、陰陽の流れが滞り、健康や運勢に悪影響を及ぼすとされています。
廃墟や墓地
廃墟や墓地の近くに家を建てると、陰陽の流れが悪くなり、家族間のトラブルや災いを招きます。
これらの悪い地相は、風水においては煩い(ファン)と呼ばれ、運気を下げるものとされています。 適切な対策を行うことで、悪い地相を吉相に転じさせることも可能です。
何よりも大切なのは、土地の「気」

「よい土地」とは何なのでしょうか?一言でいえば、よい「気」をはらんでいる土地のことです。もう少し説明するなら、「地のエネルギー」が強く、そのエネルギーがうまくたまるようになっている場所のこと。もちろん、どんな土地にも地のエネルギーは存在しますが、その強さは場所によって大きな差があります。特に地のエネルギーに勢いのある場所が、よい気に満ちた土地といえるわけです。
もっとわかりやすく言うなら、「あの街には活気がある」「あの街はさびれている」といった表現は、私たちが土地の「気」を感じている証拠です。よい気に満ちた地とは、パワーのある土地のことです。そうした上地は、多くの人を惹きつけていきます。人が住みつき、また人が集まり、発展して大都市になっていく、という歴史をたどってきた土地は、よい気に満ちているものです。
歴史的によい土地とは日当たりのいい南向き
ここでは個々の土地の見分け方に入る前に、ご参考までに、風水が歴史的に「よい土地」としてきた条件をご紹介しておきましょう。これはひとつの都市ぐらいの広さの土地についていえることなのですが、風水の基礎ですので、頭に入れておくといいでしょう。
まずひとつめのポイントは、「肥沃な土地」であることです。エジプトや黄河など、古来、人類が文明を築いてきたのは、いずれも河のほとりの肥沃な土地でした。河のほとりは作物が豊かに実る土地、つまり「財の貯まる土地」だったのです。逆に「やせた土地」は凶とされてきました。
そして2つ目のポイントは、「日当たりのよい土地」であることです。これも作物に必要な条件で、南に向かって開けた土地が奸まれるようになりました。さらに北からの冷たい風をさえぎる必要もあったため、北側がふさがれている土地が好まれました。こうして結果的に、「北がふさがれていて、南に開けている土地」が理想とされたわけです。さて、いかがでしょうか。なかなか難しそうな条件に思えますが、巫刄や京都など長く都として繁栄した土地は、見事にこれらの条件を満たしています。もちろん、みなさん全貝が農業にたずさわるわけではないかもしれませんが、でもこれらの風水の伝統は、意外にも現代社会にも当てはまることが多いものです。南向きの明るい土地は今も多くの人を呼び寄せて栄えますし、やせた上地の開運度は今ひとつと言えるでしょう。
土地選びには7つのチェックが大切

①自分で「よい気」を感じられますか?
②土地の歴史はよいものですか?
③地形は安全ですか?
④敷地の形は整つていますか?
⑤道路との関係は良好ですか?
⑥近所の人はよい気を発していますか?
これらの条件にすべて「Yes」と答えることができれば、その土地は「よい気」に満ちた土地だと思っていいでしょう。
自分で「よい気」を感じる土地が理想
最も大切なのは、ご自分で「よい気」を感じる土地を選ぶことです。何となくジメジメしているそこに立つとヒンヤリするなぜか近所の家が汚れている、生気が感じられない、そういった土地は絶対に避けることです。逆に、あったかい感じがしたり、明るい雰囲気のある土地は、よい気が満ちている証拠なのです。
重要なのは、ちょっとでも何か気になると思ったら、考え直してみること。とにかく一生住む場所なのですから、自分かどう感じるかは大切なことです。自分のカンだけでは心もとない、というのでしたら、おすすめの方法は、小さなお子さんを連れていくことです。そして反応を見てください。子どもは「気」に敏感なもの。むずかったりする土地は、何か問題がある証拠です。子どもが気に入り、そこで遊びたがるような土地なら、安心して選んで間違いありません。さらに、晴れた日のお昼にだけ見に行くのではなく、条件を変えて何度も見に行くことも大切です。雨の日や、曇りの日、夕方や、夜にも行って見てみる。どんなときでもよい印象を持てる土地が、本当の意味でのよい気に満ちた土地なのです。
土地の「来歴」をチェックする
どんな土地にも「物語」があります。今は住宅街でも昔はお墓や火葬場だった、といった土地もないわけではありません。その土地の歴史を知ることは重要な作業です。まずは、土地の名前をチェックすることです。たとえば「江」「沼」などの文字がつく名前なら、昔はジメジメした湿地たった可能性があります。大雨のときにトラブルが起こることも考えられます。「古地図」を調べるのも非常に参考になります。時代をさかのぼると、昔その土地に何かあったかが一目瞭然です。「言い伝え」も有力な情報。古戦場や刑場の後などは、やはりよい土地とは言えないものです。さらに、できれば近所の人に、その土地にまつわる話を聞くといいでしょう。その土地のことは、そこに住む人に聞いたり、飲食店に入って話を聞いたりすれば、自然に情報収集ができるはずです。過去の事件や事故についてなど、生の声が一番です。
「吉相」の土地と「凶相」の土地
家の方位はいいはずなのに、なぜかトラブルが多い・・・その原因は、立地条件にあるのかもしれません。人が家の持つ「気」の影響を受けるように、家は土地が発する「気」の影響を受けるのです。風水というと、つい方位や色のことばかりに目がいってしまいがちですが、実はどんな土地に建っているかということも、重要なチェックポイントになります。もともと風水は大地に脈々と流れる気によって、吉凶を判断していったことがはじまりでした。「地理風水」という言葉が昔からあるくらい土地が家や人に与える影響は、非常に大きなものなのです。新しく家を建てたり、引つ越したりする際には、まずはじめに土地の吉凶から見ていきましょう。原則として土地は、日当たり、風通し、水はけがよいことが最低条件。この3点に加えて、下で紹介する吉相と凶相の項目をチェックしてください。
吉相の土地
●傾斜のある土地
南(前)が低く、北(後ろ)が高い傾斜地は大吉の地相。さらに、背後に山や丘があれば最高です。これは風水で理想の環境とする「龍穴」の地形。逆に、南が高く、北が低い場合は大凶となります。
●敷地が変形していない
幸運を呼ぶ地相の条件は、変形がないこと。理想は正方形や長方形の土地です。
●川が近くにある
澄んだ水は人の心を癒し、運を呼びこむパワーを持っています。ただし、川の水が汚れている場合は凶作用が強くなります。また、河川や湖などと近づきすぎている場合も、洪水の心配などがあるので避けるべきです。
凶相の土地
●造成地にある
森林を伐採したり、海岸線などを埋め立ててつくる土地は、当然ですが自然の理に反したもので風水的には全く好ましくありません。
●三角形の土地
変形している土地は全般的によくありませんが、中でも三角形は要注意。特に頂点が前になっている場合は、災厄を呼ぶ原因になります。
●隣の土地と高低差がある
高低が2m以上ある場合は、低いほうにある土地のエネルギーが不足してしまいます。
●火事で燃えた土地
土壌の状態が悪く、大地からの気を十分に吸収することができません。
太陽光が重要
東南の角地
家を建てるとき第一に考えるのは、太陽光をいかに上手に取り込むかです。太陽光は、家を明るく暖かくするだけでなく、紫外線による殺菌作用や、光が降り注ぐだけで精神的な安定感をも得られます。太陽光は、地球上の万物を育てる光と熱の源で、動植物の成長にもなくてはならないことはいうまでもありません。分譲地では、家相上も吉とされる太陽光を十分に取り込める「東南の角地」が価格も高く、人気がありますが、その土地にも長所・短所があります。長所は、東と南に家が隣接していないので、十分な採光が得られること。短所は、南側に通りからの視線をさえぎる必要が生まれることです。このことを確認して土地を選びましょう。
さらに、風水家相上ではありませんが、建ぺい率や容積率、斜線制限などの建築的な土地の制約もしっかりと調べておきたいものです。北側斜線などの制限があればあるほど、間取りは制約を受ける場合があります。しかし逆に、住宅地としては、制限が厳しいほど吉といえます。なぜなら、快適な住環境をつくるために、規制を厳しくしているからです。周辺の家も、それらの制限を守りますから、将来も周辺環境のよい吉相の家となります。
南に余裕のある土地
東南の角地とともに、風水家相では南側に余裕のある敷地を、太陽光に満ちた吉の土地としています。「離の方向に空地あるのは、吉相と知るべし」と家相学の古書にもハッキリと記されています。南側に余裕がある敷地は太陽光を存分に取り入れられるばかりではなく、通風も非常によいのです。吉田兼好の『徒然草』にも「住まいは夏を旨とすべし」と書かれているように、高温多湿の日本にとって、住宅設備や空調機のない時代では、夏をいかにしのぎやすく住むかが重要な条件になっていました
南の方位に余裕があれば、夏は南西から涼しくてさわやかな風を家の中に取り入れることができ、南側に余裕があれば、南の開口部を広く取ってもプライバシーが守られます。部屋の間取りのしやすさなど、吉相の家づくりができる条件がそろっています。南側に大きな開口部をつくる利点は、ほかにもたくさんあります。まず、冬でも暖かいこと。冬は太陽光が40度近くに下がりますから、家の奥深くまで太陽の光が差し込み、冬でも暖かく、光熱費も少なくてすみます。また、夏は太陽が80度近くに昇るため、意外に室内に光は入りません。ですから、明るさを確保でき、それほど暑くはならないのです。深いひさしや縁側があれば、夏の強い日差しが室内に入り込むのを避けることができます
土地の傾斜で 吉凶が変わる
土地は傾斜によっても吉凶が大きく異なってきます。家相学では、傾斜とは「ゆるやかな傾斜」をいい、土地の高低によって、よし悪しを判断しています。なかでも最良の土地は平坦地で、次に、朝日を効率よく取り入れられる「東側が低い土地」「南側が低い土地」や、「南東が低い土地」を吉としています。とくに、東側が低い土地は、隣家が西日をさえぎってくれるため、大吉の土地とされ、南側が低い土地は、北側が高ければ、冬の北風をさえぎることができ、吉としてきました。
西や北側が低い土地は日当たりが悪く凶
凶相の敷地とは、朝日が入りにくく、西日に悩まされる「西側が低い土地」や、日当たりが惡く、冬は北風をまともに受けて寒い「北側が低い土地」、湿気がたまり、人目も気になる「周囲よりも低い土地」です。また、家相書では、「北東が欠けるのは凶」など、土地に張り、欠けの多い凹凸形の不整形な土地を凶としています。
なお、吉の土地としては、この二例のほか、平坦地と南東が低く北西が高い土地があり、凶の土地には、三例のほかに、中央が高い土地、南が低く三方が高い土地があります。
土地の高低だけでなく周辺環境も大事
しかし、土地の高低だけでは家相は語れません。周辺環境が大事だということを知っておきましょう。例えば、住民のゴミ出しのマナーや、土地が昔どのように使用されていたかも調べておきましょう。工場跡地などは健康面での心配があります。周辺環境については、新興住宅地よりも、年を経た落ち着いた住宅地のほうが、住人から住み心地や、生活面のことなどを聞くことができ、より吉の土地選びができるでしょう。
道路付けで 変わる吉凶
平坦な土地でも、周辺の環境によって吉凶が決まります。建物の道路付けがそのひとつです。とくに、悪条件の土地は、道路状況で改善をすることができます。
土地と道路状況の関係
たとえば、北東方向に斜めの道路であれば、東の光が当たりやすくなり吉です。また、平坦地ではなく東側が低い場合には、より採光のよい吉相の土地となります。逆に、凶となる土地は、北西方向に斜めの道路です。北西方向に道路がある状況では、西日を取り込みやすくなってしまいます。この場合は、隣家との位置関係に注意して、西日がまともに当たる窓を小さくして、遮熱ガラスを採用するなどの配慮が必要になります。
ここでは、六区画の分譲地を例に、採光・通風のよい吉相の土地を、道路付け別に説明しました。また、悪い土地でも、土地、建物の面積や家のつくりで、採光のよい吉相に変えることができる方法を解説しました。
路地は私道か、公道かを確認する
道路には、公道と私道があります。私道は私人が保持管理し通行路として使用します。土地 の一部に私道が含まれる場合は「私道負担金」 が必要なのです。しかし、所有権はあっても勝手に建物 を建てたり、門や塀、花壇などをつくることは出来ないのです。実際に使える部分は、私道以外に なります。公道に面した土地よりも不利な条件になります。購入に当たっては、役所で十分に 調べることが非常に重要です。
軟弱地盤は避けるべき
地盤の弱い土地に建物をつくると、不同沈下によって、徐々に建物が傾く可能性が大いにあります。さらには、大規模な造成地では、「切り土」「盛り上」などの造成工事によって、地盤の強度が大きく変わってきます。既存の斜面に新しく上を盛ったり、埋め立てたりする「盛り上」の土地よりも、古い地盤の斜面を削り取った「切り上」のほうが圧倒的に安全なのです。また、盛り土の場合は沈下が起きやすく、また、地盤が安定するまでにかなり時間がかかります。
地名で軟弱地盤を知る
古くからの地名によって、地盤の強弱を判断することもできます。「沼、水、谷、田、江、湖」などがつく地名は低湿地、「沖、州、由、須賀」などがつく地名は、干拓地や干潟などです。とくに、水に関する名前がついている場合は、洪水などの心配や湿潤地であることが多いので、過去に、洪水や崖崩れが起きていないかを役所で調べておくべきです。
※記事内には「PR」の宣伝活動および、アフィリエイト広告が含まれております。

